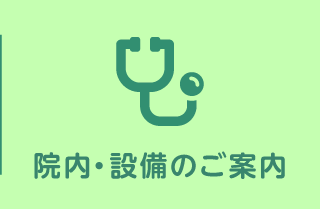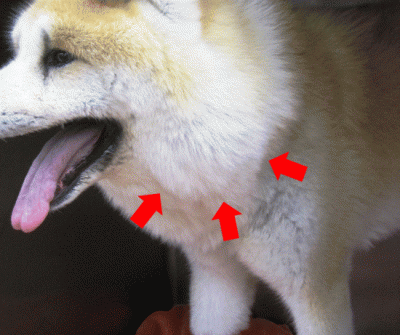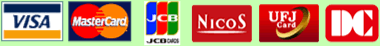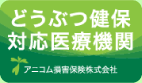ヒトではバセドウ病(グレーブス病)や原発事故に伴う放射性ヨウ素の問題など、
何かと話題になる『甲状腺』。
私たち獣医の領域でも、甲状腺にかかわる疾病は比較的多く遭遇するものの一つです。
特に、犬の甲状腺機能低下症・猫の甲状腺機能亢進症の二つは発生頻度も高く、
耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は症例を犬の甲状腺疾患に絞って、少しだけご紹介したいと思います。
①犬の甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンは全身で様々な役割を担っているため、その分泌が低下した際の症状も非常に多岐にわたります。
その中でも、おそらく飼い主さんが最も気づきやすい症状は皮膚の変化ではないでしょうか。
下の写真は、私が診察させていただいたコッカー・スパニエルのワンちゃんの治療前写真です。
『ラットテール』と呼ばれる典型的な尾の脱毛が起きているのがわかります。
(ラット、つまりドブネズミは尻尾に毛が生えていないことに由来します)
注意:毛を刈っているわけではなく脱毛しています
下の写真が、甲状腺製剤による治療を行なった後の同じ犬の写真です。
こうした皮膚病変は、私の経験では治療開始後1か月以内に改善がみられます。
また甲状腺機能低下症は、神経症状として現れることがあります。
特に甲状腺機能低下症によるニューロミオパチー(hypothyroid neuromyopathy)は、
進行性の四肢不全麻痺・筋委縮・脊髄反射低下などを引き起こす恐ろしい病気です。
これらの神経症状は、前述した脱毛などを伴わずに発症するため、
外観からは甲状腺が原因とわからないケースが多いため注意が必要です。
●Euthyroid sick syndromeについて
また余談ですが、甲状腺機能低下症と誤診されやすいeuthyroid sick syndrome(ユーサイロイド・シック・シンドローム)という状態があります。
これは何らかの病気にかかった際に、身体が意図的に甲状腺ホルモン濃度を低下させるものです。
いわば代謝を落として身体を休ませる現象なのですが、甲状腺ホルモンを測定すると低値を示すことからeuthyroid sick syndromeが甲状腺機能低下症と誤診されるケースもあるため注意が必要です。
euthyroid sick syndromeの場合は、その基礎疾患を治療することが優先です。
②犬の甲状腺癌
犬の甲状腺癌は大型になることが多いため、「頸部のしこり」として飼い主さんが見つけることが多い腫瘍です。
(同じく「頸部のしこり」として犬で発生の多いものに、多中心型リンパ腫や唾液腺嚢胞があります)
甲状腺は組織学的に濾胞細胞とC細胞により構成されており、そのぞれぞれから悪性腫瘍が発生します。(濾胞細胞の悪性腫瘍☞濾胞細胞癌 / C細胞の悪性腫瘍☞C細胞癌)
下の写真は、以前治療させていただいた甲状腺濾胞細胞癌の秋田犬です。
左下顎領域に『こぶし大』の巨大な腫瘤が形成されています。
犬の甲状腺癌は、摘出可能な場合は外科摘出を目指し、固着している場合は放射線治療が選択されます。
(上の症例では発見時に既に腫瘍が固着しており、放射線治療を実施しました)
実は犬の甲状腺癌は、前述した甲状腺機能低下症と無関係ではありません。
特にビーグルの場合は甲状腺機能低下症から甲状腺癌へと進行する可能性が高いことがわかっています( Benjamin SA et al., Vet Ohatol 33, 486-494 (1996) )。
これは甲状腺低下症を無治療で放置した結果、脳から分泌される甲状腺刺激ホルモンによって慢性的に甲状腺が刺激されることによって起きると考えられています(衰えた甲状腺に鞭を打っている状態ですね)。
最後になりましたが、犬の甲状腺機能低下症はその症状の多様さやeuthyroid sick syndromeの存在から、診断に注意を要する病気の一つです。
しかし甲状腺癌に進行するケースや、発作など危険な症状を引き起こすこともあることから、正確な診断と早期の治療開始が非常に重要であることは間違いありません。
診断が手遅れにならないように、あるいは過剰診断にならないように、かかりつけの獣医師とよく相談して愛犬の治療をしてあげてくださいね。